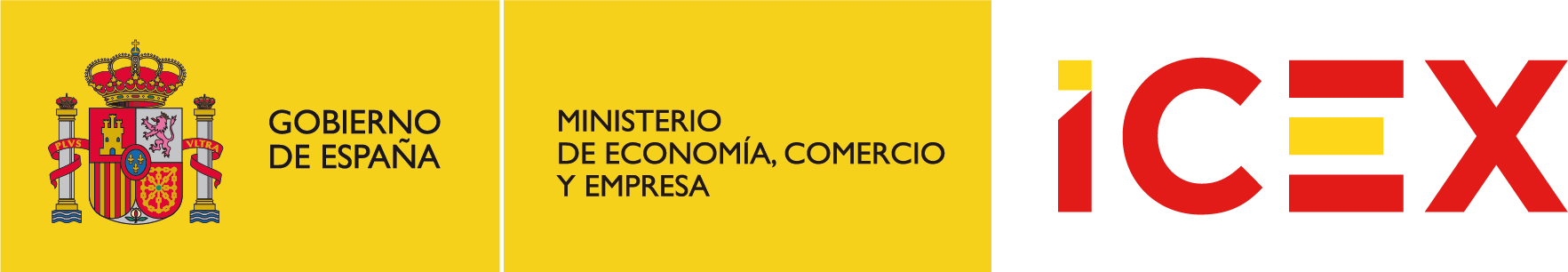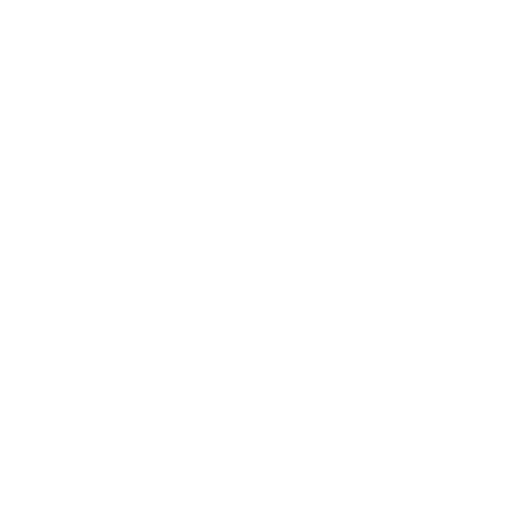スペインの古典から現代までの文学を幅広く翻訳・研究・指導してらっしゃる清泉女子大学の吉田彩子先生に、スペイン文学の楽しみ方についてお話を伺いました。
生涯の研究テーマ、詩人ルイス・デ・ゴンゴラ
私が研究しているルイス・デ・ゴンゴラ(1561-1627年)は、「黄金世紀」と呼ばれた16・17世紀のスペインの詩人で、セルバンテスより14歳若いコルドバの聖職者でした。文学界ではピカレスク小説が流行し、ゴンゴラだけでなく、セルバンテス、劇作家のローペ・デ・ベガやカルデロン、美術ではベラスケス、エル・グレコなどが活躍した輝かしい時代です。
古川日出男さんが、ノーベル賞作家ガブリエル・ガルシア=マルケスの『百年の孤独』を読んでいなかったら、『聖家族』や『ベルカ、吠えないのか?』も生まれなかったかもしれない? マルケスの世界観を彷彿させる、独特のパンチがきいた文体とスケールの大きさが印象的な作品を発表されている古川さんにご寄稿いただきました。
スペイン「語」が孕んでいたもの
スペインとは、僕には言語であって国家ではない。このことは驚異的だ。もちろん同じことは英語に関しても起きている。僕は英語からイギリスという国家を「想う」ことがない。むしろ英語はつねにアメリカに結ばれていた(これはもしかしたら平均的な日本人の感性ではないか、とも感じる)。おかしな話なのだけれど。どうしてイギリスの言語が、アメリカの国家のものになっているのか?
この背景にあるのは「帝国」という概念、歴史だ。