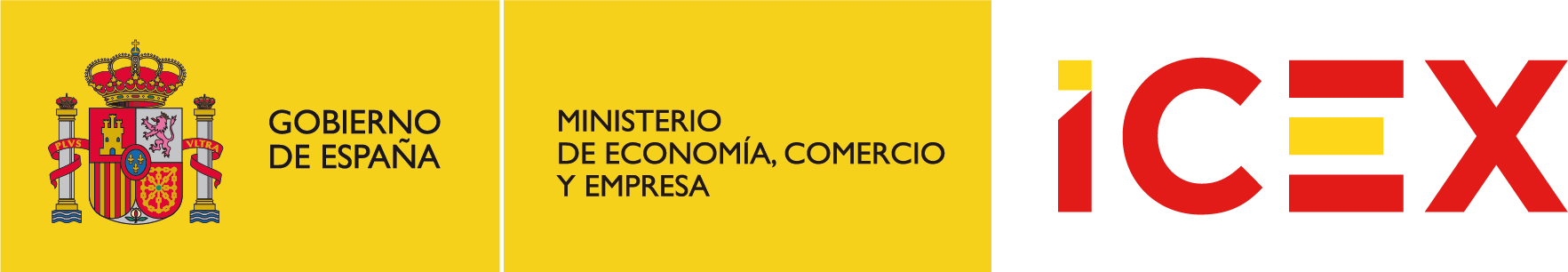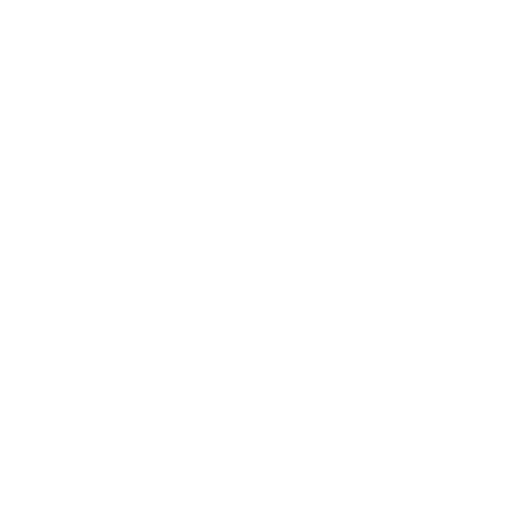■概要
高齢の女性5人が共同生活をするマドリードのマンションに、9月のある日、一人の若い娘が現れる。彼女は、どのようにしてここに来たのか、なぜいるのか自分自身でも分からないが、そのまま婦人たちと一緒に住み始める。娘の視点から、日々の食事や、歯に衣着せぬおしゃべり、毎週金曜日に居間で行われる自宅美容室、言葉の録音テープを納めた箱、独自の分類をした図書室など、共同生活の様子が語られる一方で、婦人たちが娘に語りかける形式で、それぞれの人生が明かされていく。一人の婦人の死を機に、娘は自分の居場所を見つけ、何をすべきかを考え始める。そして9月、マンションに新たな住人が現れる。
■主な登場人物
主人公:若い独身の女性。名前とこの家に来るまでの詳細は不明。1990年代に子ども時代を過ごしている。
ロサリオ(カトリックで使う数珠の意):この家の住人。96歳の女性。5人の中で一番背が低い。
エスメラルダ(鉱物のエメラルドの意):この家の住人。一番背が高い女性。ドライで不愛想。いつも緑色の服を着ている。
オルビド(忘却の意):この家の住人。79歳。忘れっぽい。
パロマ(鳩の意):この家の住人。一見物静かだが、的確で鋭いコメントをする。
アスセナ(白百合の意):この家の住人。5人の中の最年少。唯一、髪が長い。
■あらすじ
自分の家のソファでくつろいでいたはずのわたしは、突然、5人のご婦人方が共同生活をする家のソファに座っていた。どうやって、なぜここに来たのかは分からないが、5人はわたしの存在を意に介していない様子だ。ひとしきりおしゃべりに興じた後、突然わたしに向かって声を揃えて言った。「疲れた様子ね。わたしたちも9月にここに来たのよ。ようこそいらっしゃいました。あなたの部屋に案内するわね。」
翌朝目覚めると、部屋の洋服ダンスには自分の服が、本棚には自分の本が並んでいるのを目にした。不思議に感じつつも、浴室に行こうと部屋を出たとき、この家の住人のひとり、ロサリオに引き留められ、この家に来る前の彼女の人生を語られる。ロサリオは、9人兄妹の末っ子で、生まれ故郷で両親を看取った後、首都マドリードに出てきた。人形劇団のお針子として働き始めたロサリオは、そこでグロリアに出会い、恋に落ちる。二人はグロリアが亡くなるまで一緒に住んでいた。その後、ロサリオはこの家にやってきたのだった。ロサリオに言われるまま、わたしは彼女と一緒にポラロイド写真を撮る。解放されたわたしは、浴室に行って、入浴をするが、ここでも、自分の名前が書かれた引き出しを見つける(まだ名乗っていないのに)。また、ご婦人方が世界中の旅行で買い集めてきた浴用品の数々や、たくさんの本や雑誌も目にする。
浴室を出ると、再びロサリオに出くわす。ちょうどそのとき、玄関に食料の箱が届けられる。わたしは箱を台所に運ばされる。エスメラルダとオルビドが音もたてずにやってきていて、次回からは自分の買い物リストを作るように言われる。その後、オルビドと一緒にわたしは居間にいく。新し物好きのオルビドは、若いわたしと最近の事柄について語りたいようだ。そして、昔の話もしてくれる。オルビドは小さいころから「独身女性」になりたがっていた。また、若いころに新聞の売店で働いていて、そこにきた子どもを追い払ったことがきっかけで「ほうきおばさん」というあだ名で呼ばれていた。彼女自身は、独身の、魔女のように聞こえるので、このあだ名が気に入っていた。
その後、オルビドは、居間にある「言葉箱」をわたしに見せてくれる。その中には、雑誌や新聞の切り抜きから、紙切れに書いたものまで、たくさんの言葉がファイルされ、さらにそれがアルファベット別のテープに録音されている。また、各人が好きな言葉を録音するテープも人数分揃っていた。オルビドに言われるまま、辞書から見つけた言葉を録音したわたしは、この行為で、この家の住人になる署名をしたようなものだと思った。
アスセナとパロマにも会ったわたしは、それぞれの名は体を表していると考えた。
午後1時になり、居間では昼食が始まった。ご婦人方は無口で真剣に食べている。朝は、ロサリオが一番早く起きて朝食の準備を始める一方で、オルビドが身づくろいもせずに一番最後にやってくる。朝食後、ピアノを弾いたり、書き物をしたり、それぞれが好きなことをして過ごす。昼食後はおしゃべりだ。昼寝をすることもあるし、ヨガをしたり読書したりする人もいる。そうこうするうちに夕食の準備が始まる。夕食後は各自の部屋で過ごすが、皆明け方まで眠れない。
アスセナはヨガをしながら、その昔教師をしていた頃の話をわたしにする。また、自分がベジタリアンになった経緯や、退職後にインドにいってヨガとシタールを習った話をした。
月に一度、ご婦人方はテーブルを囲んで物語を語り合う会を行う。逸話だったり、童話のパクリだったりするが、皆が好きなキャラクターは、赤ずきんだ。5人がそれぞれのバージョンの赤ずきんを語り終えた後、わたしが話をする番になる。頭が真っ白になったわたしは、祖父の靴下が入っていた引き出しの話をする。
わたしはこの家の図書室を紹介される。分類方法が独特で、著者の第一姓ではなく、第二姓で分類するのだ(注:スペインでは、父親と母親からそれぞれ受け継いだ姓が子の姓になる。父親からの姓がメインで一番目に、母親からの姓が二番目に来る)。ご婦人方は、週に一度、好きな本を読んで皆に紹介する読書会を行っている。居間には書き物机があって、皆で共有している。ほとんどが家の中で過ごすが、時には散歩に出かけることもあるし、以前は皆で海外旅行に行ったりもした。
パロマが昔の話をしてくれる。彼女はマドリードの地下鉄の切符売りを仕事としていた。定年まで働いて、この家に来たのだった。
この家の冷蔵庫に貼ってある「戒律」はこうだ。「汝、許可を求めるなかれ。」この戒律は、ご婦人方が思いつく限りの好意を、何の気兼ねもなく互いに求め合うことを認めている。わたしはここに来てからというもの、皆の使い走りのような立場だ。そんなわけで、エスメラルダにコーヒーを用意している間、彼女の話を聞いた。
エスメラルダは自然豊かなカンタブリア州の国道沿いの家に住んでいた。そこでは、パンを作ったり、かぎ針編みをしたり、穏やかに暮らしていたのだが、あるときマドリードにやってきて、自分より高齢の女性と一緒に住み始めた。女性は、エスメラルダ曰く、精神的にも高齢だった。テレビを見て過ごし、飼っているカナリアに話しかける日々。籠に閉じ込められたカナリアは次第に弱っていき、ある日姿が見えなくなった。それを潮時に、エスメラルダはこの家にやってきた。そして、長いこと自分たちの話を聞いてくれる人がいなかったから、わたしたちは今この家でたくさん話しているのだ、とエスメラルダはいう。
精神的に若いご婦人方は、インターネットに興味津々で、わたしにインターネットを教えろと乞うてきた。基本的なことを習って数日のうちに、メールアドレスを作ったりネットで情報を見たりするだけでなく、インスタグラムやYou Tubeのアカウントを作って情報発信したり、自分が作った小物をネットで売り出したりし始めた。
金曜日には、ご婦人方は居間を自宅美容室に変えて、お互いに髪を切ったり、洗ったり、毛染めしたりすることにしている。アスセナだけは自分で洗って自分で梳かし、決して切らない。わたしはアスセナに頼んで短く切ることにする。
ある晩、暑さと蚊のせいで眠れないわたしは、水を飲みに台所に行った。そこでロサリオと出くわす。ロサリオに誘われて一緒に居間に行く。そこで、ロサリオは、まさか自分の人生がこんなことになるとは、この家に来ることになるとは想像もしていなかったと語りだし、わたしに対し、人生を楽しめ、と話す。気分が悪くなったロサリオは、ベッドまで連れていくようわたしに願い、その途中で見かけた二人が写るポラロイド写真を見て、フォトフレームを買うようにと言った。ロサリオは、グロリアが死んだ直後に夢に出てきた話をしながら、なんとかベッドにたどり着く。そして、自分が死んだら、決してあなたを驚かせたりしないように会いに行くから、とわたしに約束をし、テレビが消えるときのように、息を引き取った。
ご婦人方の誰かが亡くなったときは、中二階に「埋葬」される。ロサリオも同様に「埋葬」された。残った女性たちは、歌い、泣き、窓を開けて外の空気を吸い込み、お互いに抱き合う。
エスメラルダに「あなたが来てくれてよかった」といわれ、居場所を見つけたと感じるわたし。そしてうたた寝をしたときに、夢にロサリオが現れて、こう問いかける。「地球での自分の時間で何をするつもりなの?」
再び9月、皆でコーヒーを飲みながらおしゃべりをしていると、ドアをノックする音がする。玄関には、小さな女の子が立っていて、チョコレートを持ってきたから中に入れてくれという。5人で、小さい子どもがいることなど気にせず、ひとしきりおしゃべりに興じた後、女の子があくびをしているのに気づく。そして声を揃えていった。「疲れた様子ね。わたしたちも9月にここに来たのよ。ようこそいらっしゃいました。あなたの部屋に案内するわね。」
■所感・評価
気心の知れた女同士、自由気ままな共同生活をしながら、余生を送る。老後をどうしよう、と考えたとき、この本の5人の老婦人の「シェアハウス」は、洋の東西を問わず、ひとつの理想かもしれない。そう思わせるのは、婦人たちの暮らしぶり(と往生の仕方)のせいだ。たわいないけれど心から楽しんでいる会話、自由気ままな日課、皆で取り組んでいる蔵書管理や「言葉の箱」の整理、インターネットへの挑戦など、5人で合わせて400歳を超えるという年齢にもかかわらず、常に前向きで活動的に描かれた姿は、エネルギーを与えてくれ、前向きな気持ちにしてくれる。それは、この本の主人公で、いつのまにか婦人たちの家にやってきていた若い女性にとっても同様だ。最後まで名前は明かされず、また、婦人たちが自らの過去を語るのとは対照的に、主人公がこの家に来るまでの状況などは、ほとんど明かされない。結局最後まで主人公については謎が多いままだが、物語冒頭には単なる聞き役という印象だったのが、ロサリオの死を機に、ご婦人方の一員となり、しっかりと居場所を見つけ、自分がすべきことを考え始めるのだ。
物語は、それぞれ見出しがついた短い章(原文2~5ページ程度)で成り立っている。多言語に精通した翻訳家である著者は、ご婦人方が行った旅行のお土産品の説明から、ハリウッド映画や書籍、化粧品、シャンソンなど、古今東西の文化を登場人物の心情や状況説明に使っている。これらの小道具の多くは、日本でも馴染みのあるものだが、一方で、スペインの一地方の事物などは、訳注を追加しても良いだろう。
想定される読者層は、やはり、女性だろう。1986年生まれの著者と同年代から、ロサリオと同年代まで、日本の読者にも、元気なおばあちゃんたちから元気をもらう読書体験をしてもらいたい。
■試訳(71ページから74ページ)
パロマ
1919年、マドリードで最初の地下鉄が開通しました。ソルからクアトロ・カミノスまででした。大戦間に建てられたから、材料はすべて国産でした。鉄はビルバオから、タイルはセビリアから、セメントタイルはカタルーニャから持ってきたのよ。結婚している女性は外で働くことができなかったので、切符売り場では若い女性だけが働いていました。その女性の一人がわたしでした。
今はもうないチャンベリ駅で切符売りをしていたんです。まあ、今でもあるわね、博物館としてね。1号線に乗って、ビルバオとイグレシアの間に見えるのだけれど、ほとんど誰も気づかず、見逃しちゃうでしょう。幽霊駅と呼ばれているのです。80年代には大騒ぎになっていました。ジャンキーたちがクスリを打ちにやってきていて、そのあまりのやつれた顔を見て、人によってはショックを受けたものです。皆彼らをゾンビだと考えていたけれど、ある意味確かにゾンビだった。
わたしが仕事を始めたのは、戦争、つまりわたしたちの戦争、いや、彼らの戦争、それを始めた人たちの戦争からずいぶん経った後でした。あのひどい数年間、チャンベリ駅は爆撃と恐怖から逃れるために多くの男女が避難する場所として機能していました。
66年に閉鎖され、そのまま残っています。もちろん、修復されたのだけど、広告は当時のままのタイル製で、日ごとに変えられるような代物ではありません。そして、ガル(訳注:化粧品会社)は、無意識のうちに、その歴史の中で最高の投資をしたんじゃないかと思います。ガルが売ったワセリンのケースの数で、十分、元が取れていますから。わたしは全部持ってます。アールヌーボコレクション全部と、アガサ・ルイス・デ・ラ・プラダのもの全部ね。でも、一番好きなのは、いつも売っている、蓋がピンクで、下の容器がほとんど赤の濃いピンク色で、側面が波打ってるやつなんだけど、どれだかわかる? そう、いつも売っているあれよ。とってもいいわよね。ただ、ケースを床に落とすと、蓋が割れてしまうことがあります。いくつかセロハンテープで貼り付けたんだけど、製品が長持ちするので、結局セロハンテープが黄色く変色して粘着力がなくなって、とても汚くてだらしないイメージになってしまうので、貼り替えなければならないのです。まあ、ホントだ、話がそれてしまったわね。さて、わたしはチャンベリ駅で切符売りとして働いていたのだけれど、まるで未来、進歩を見に来たような感じでした。しかも、切符売り場は、天井に採光窓があって光が入り、まるで街路にいるような感じで、なかなか気持ちがよかった。もちろん、凍えるような寒さで、暖房器具を使っても、手をこすり合わせても、温かいスープを飲んでも、どうにもならないときもあったけど。
一日にどれだけたくさんの切符を売ったのか分かりません。おそらく、ものすごく多いというほどではなかったかもしれないけど、結構な量でした。毎日、たくさんのいろんな顔がやってくる。たくさんの同じような顔がやってくる。だから人を見るのが嫌になったのよ。ナンパ目的で来たとしか思えないような男性もいて、中には成功した人もいました。同僚が結婚すると、二度と会えなくなり、残念でしたね。既婚女性が働くには夫の許可が必要で、たとえ許可があってもなかなか働けなかった。それに、地下鉄でナンパをするような男たちは、もちろん妻がそこで自分のようなごろつきの目に晒されることを嫌ったのだろうとは想像できます。わたしは結婚しなかった、全く知らないそういう男の人たちの一人と結婚する気はなかったのです。
閉鎖されるまでチャンベリ駅にいたのですが、その後イグレシア駅に異動になりました。退職してほぼすぐにこの家に来ました。わたしもあなたと同じように、何をするのかよくわからないまま、ここに来ました。わたしが住んでいたのはこの下の階でしたが、同じようでいて全く違う、つまり間取りは同じでも装飾は全く違うのです。ある日、ここに来て、ロサリオがわたしの部屋を見せてくれたとき、そこにはわたしのすべての物があり、わたしは恐怖で死ぬのか、それとも幸せなのか、何だか分からなくなりました。わたしは後者を選んだ。アパートで退屈していたからね。わたしの友人たちは死んでしまったか、あるいはつまらないことをしているか、わたしたちが若かった頃を真似たような番組を見ているだけでした。テレビ小説と呼ばれているけど、読むためのものではない。ああ、なんて惨めなんでしょう。男だけに自由があった、まあ、たいして自由でもなかったんだけれど、それを見るためにわざわざテレビをつけたくないわ。とにかく、わたしはここに居続けている。ピアフの歌のように「わたしは後悔していない」し、アラスカ(訳注:70年代から活動をしているスペインの女性歌手)が相変わらず歌っているように「きっともう一度同じことをするわ」。でもアラスカが歌っているような「見栄を張る」ことはしません。はるのはガルのワセリンケースに貼るセロハンテープだけです。
Feature Article
Welcome to the New Spanish Books Website, a guide to...
Interview
Helen Weir - Senior Editor at Two Hoots, an illustrated imprint of Pan Macmillan.
READ MORE
Search
Genre

BOLETIN INFORMATIVO
Suscríbete a nuestro newsletter
Haz clic aquí
SOBRE NOSOTROS
Bienvenido al sitio web de Nuevos Libros en Español, una guía para...